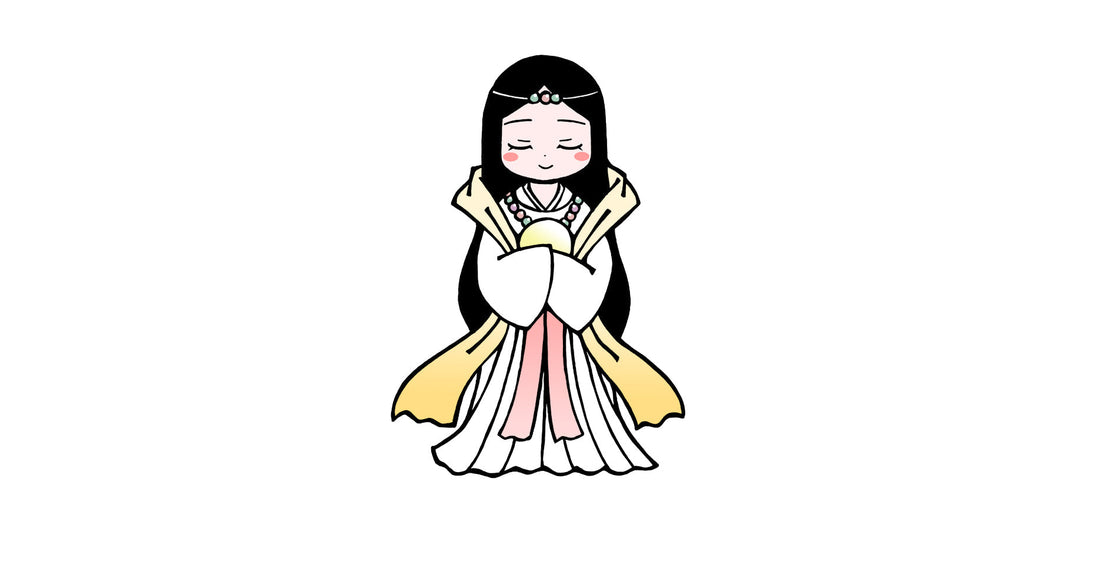
「トイレの神様」は本当にいる?いない?
はじめに:トイレの神様って本当にいる?
「トイレの神様」と聞くと、多くの方は2010年頃にトレンドになった植村花菜さんの曲『トイレの神様』を思い浮かべる方が多いかと思います。
この曲の歌詞は、トイレに「キレイな女神様がいる」というおばあちゃんの知恵、もしくは言い伝えにまつわるお話がベースになっているので、同時に「実際にトイレの神様」はいるの?いないの?と思った方も少なくなかったと思います。
そこで今回は、本当にいる『トイレの神様』についてご紹介しますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
目次
1. トイレの神様 烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)
2. 火と浄化の神 烏枢沙摩明王とは?
3. 日本への伝来と信仰の広がり
4. 「不浄を清める王」から「トイレの神様」へ
5. 現代に残る「トイレ明王」信仰のかたち
6. トイレ掃除は現代の修行? ― 清めの心を日常に
7. 携帯型トイレ掃除ミニスティックブラシ『ベンコス』
1. トイレの神様 烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)
「トイレの神様」と聞くと、どこか民話的でやさしいイメージを抱く方も多いでしょう。
しかし実際に日本で”トイレ神”として最も信仰されているのは、仏教の「五大明王」のひとり「明王烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)」です。
怒りの炎をまとい、火で穢れを焼き尽くす「明王烏枢沙摩明王」が、なぜトイレと深く結びつくようになったのか。
その歴史と信仰の広がりをたどってみましょう。

明王烏枢沙摩明王
2. 火と浄化の神 烏枢沙摩明王とは?
◎梵語名(ぼんご=サンスクリット語)「Ucchuṣma」
「明王烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)」の名は、古代インド語である梵語=サンスクリット語の “Ucchuṣma(ウッチュシュマ)” に由来します。
Ucchuṣma=意味は「熱」「焼き尽くす者」「強烈な炎をもつ者」。
もともとはインド神話の火の神アグニと関係が深く、火によって不浄を浄化する存在として信仰されていたと考えられています。
烏枢沙摩明王は、人間界と仏の世界の間にある「火生三昧(かしょうざんまい)」という炎の世界に住み、人間の煩悩が仏の世界に拡がらないよう焼き払い浄化する役割になっています。
その役割は、単に外的な汚れだけでなく、心の汚れ――嫉妬・怒り・執着といった人間の“内なる不浄”をも清めるという点にあります。
この「浄化する」ということが注目され「不浄なものを一切焼き払い清める功徳がある」と考えられていたことから、トイレを清める神様として人々には信仰されてきました。その理由は、古くから「トイレが怨霊の通り道」と考えられていたことから「怨霊を浄化してもらいたい」と願う気持ちが込められていたことによるものと考えられています。
今でも昔ながらの商家や寺院のトイレでは烏枢沙摩明王の御札が貼られていることがあります。
◎仏教における 「五大明王」とは
仏教の「五大明王」とは、密教ならではの仏である明王のうち「不動明王」「降三世明王」「軍荼利明王」「大威徳明王」「烏枢沙摩明王 または 金剛夜叉明王」のことです。それぞれ大日如来、阿閦如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来の化身とされています。
烏枢沙摩明王は、怒りの相で魔を退け、煩悩や穢れを焼き尽くす働きを担います。
3. 日本への伝来と信仰の広がり
◎密教とともに日本へ
明王烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)は、奈良〜平安時代にかけて、真言宗や天台宗といった密教の流入とともに日本へ伝わったとのことです。
当初は護摩供(ごまく)の本尊や、修法における「不浄を転じて清浄にする力」をもつ尊格として祀られていたようです。
◎清めの神としての位置づけ
伝来した当時の平安時代の頃では、出産・葬儀など“穢れを伴う儀礼”において烏枢沙摩明王が重視されていたようです。やがて、この“転不浄為清浄”の考え方が、特に“最も不浄とされた場所=トイレ”を浄化してくれる仏教の王として、人々の生活空間に取り入れられるようになって行ったとのことです。

五大明王
4. 「不浄を清める王」から「トイレの神様」へ
◎炎で清める=浄化の象徴
「明王烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)」の絵や彫刻は「背後に燃え盛る炎を背負った姿」で表されます。
この炎は“怒り”ではなく“清めの火”。
あらゆる「不浄」=“汚れ・病・悪念”を燃やして消し去る力を象徴しています。
◎「不浄」を扱う場所にこそ、清めの神を
日本では古くから、トイレ=厠(かわや)は「ケガレの溜まる場所」とされてきました。
神道では「穢れ」を避けるため、厠の神として「埴山姫神(はにやまひめ)」などの土の神を祀る風習があったようです。
そこに、仏教の5大明王の明王烏枢沙摩明王の「穢れを焼き清める」という役割が結びついた結果、烏枢沙摩明王=トイレの守護神として信仰されるようになっていったとのことです。
5. 現代に残る「トイレ明王」信仰のかたち
◎静岡・可睡斎の「大東司(だいとうす)」
「明王烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)」は、現在もトイレの守護神として祀られている例があります。
代表的なのが、静岡県袋井市の秋葉総本殿 可睡斎(かすいさい)。
境内にある「大東司(だいとうす)」には、立派な烏枢沙摩明王像が安置され、“日本一のトイレの神様”として多くの人が参拝しているとのことです。
ttps://www.kasuisai.or.jp/wp/p54
◎家庭の御札・祈りの形
一般家庭でも烏枢沙摩明王の御札や掛け軸をトイレや洗面所に祀る習慣が残っていて、多くは「お手洗い守護」「家内安全」「金運招福」といった祈願を込められているそうです。
また、風水的にもトイレの清浄は「運の流れを整える」行為とされており、掃除を通じて“心の浄化”を実践する日本人の感性と共鳴しています。

6. トイレ掃除は現代の修行? ― 清めの心を日常に
再度「明王烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)」についてまとめますと、「人間界の煩悩が仏の世界へ波及しないよう、聖なる炎によって煩悩や欲望を焼き尽くすことで浄化する」という側面と、「清浄なる自己に目覚めさせる徳を持つ」の側面の2つを担っていると考えられています。
この2つ側面からトイレについて考えると、日々のトイレ掃除は「手を動かし、空間を整えることで、自分自身の心も清らかにしていく」と考えることが出来るため、現代の一般家庭に残る修行の一部と言えそうです。
これは、トイレをきれいに保つことは、単に衛生のためだけでなく、自分の心と暮らしを整える“祈り”の形なのかもしれません。
言い換えれば、日々の生活の中にも、烏枢沙摩明王の精神が今も生きていると考えることが出来そうです。
🪷参考:
・『仏像事典』(平凡社)
・京都国立博物館「烏枢沙摩明王像」
・静岡・可睡斎公式サイト
・日本民俗学会『生活信仰における厠神の研究』
・Kotobank「烏枢沙摩明王」項目
最後に、当社で販売中のトイレアイテムの詳細をご紹介します。
1袋110円と大変お得ですので、ぜひご活用ください!
7. 外出時のトイレの必需品『ベンコス』

ベンコスは、「次の人にも綺麗な状態で、トイレを気持ちよく使って欲しい」という気持ちを実現することを考えて開発した、ミニスティック型のトイレ掃除用ブラシです。
『ベンコス』は、愛媛県より認定をいただきました!
【愛媛県】新商品生産による新事業分野開拓者認定
【ベンコスの5つのポイント!】
◎外出先でもトイレをキレイに使えます!
お友達の家のトイレや、会社のトイレで便器を汚しても大丈夫『ベンコス』があれば大丈夫! ミニスティック型なので、手を汚さず、便器の水の上の部分を『ベンコス』でキレイにお掃除することが可能です。
◎トイレに流れる!
ブラシ全体が水に溶けやすい水解紙なので、トイレに流れても落ちません!
※大量に流れてしまいますのでご注意ください。
◎パルプ100%
自然の木から作られたパルプ100%なので、自然環境に良い素材です。
◎たった10cm!のミニスティック型
ボールペンより短く、幅も1.5cm。 ポーチやバッグに入れて持ち歩くことができます!
◎安心の日本製
国内の工場で製造していますので、製品の品質の良さは抜群です! 安心してご使用いただけます。











